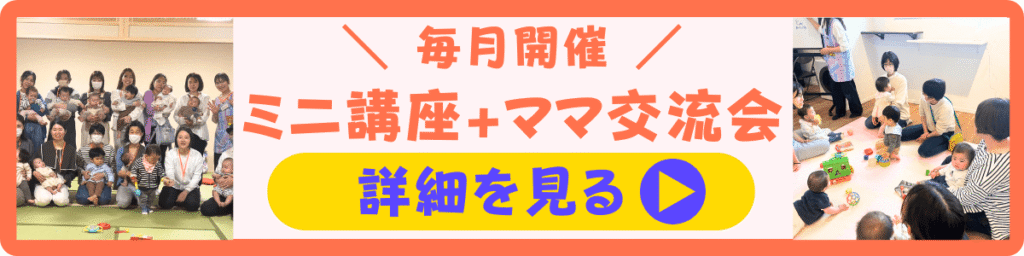
【助産師が解説】断乳とは?やり方・時期・スケジュール・ケアの完全ガイド
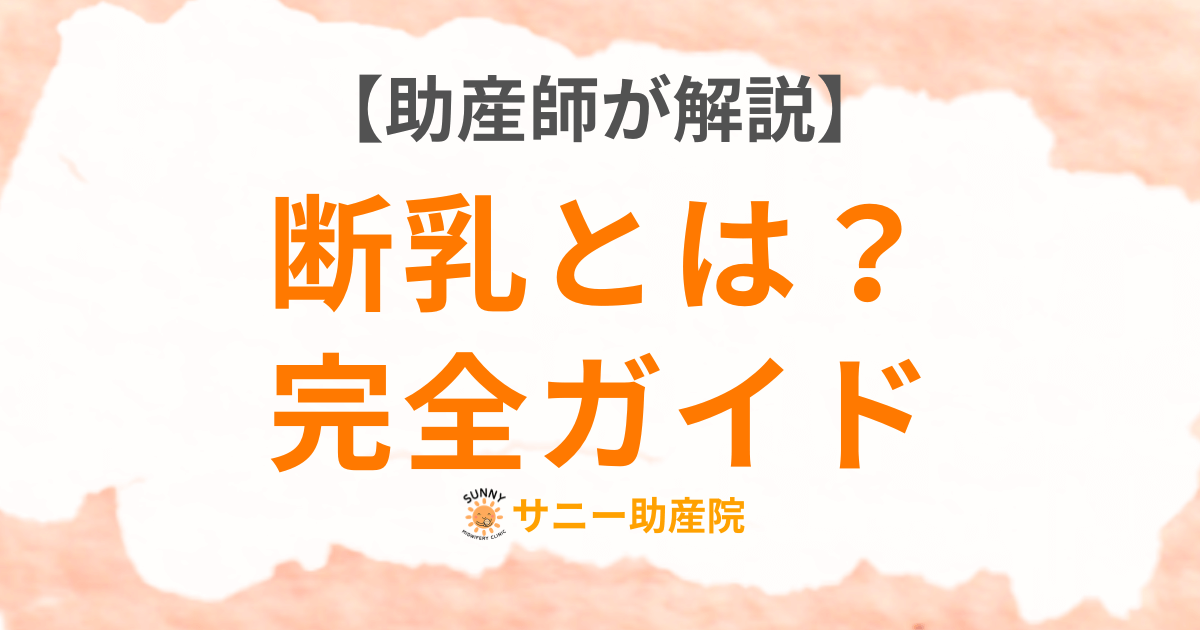
「そろそろ断乳…でも不安がいっぱい」。
断乳は赤ちゃんの成長と同時に、ママの心と体にも変化をもたらします。
この記事では、断乳とは何か、卒乳との違いを押さえつつ、やり方・いつ始めるか(時期)・スケジュールの立て方・夜間断乳・胸のケア・よくあるトラブル対処を助産師が解説します。
著者・運営者情報

院長助産師 岡田まどか
助産師歴20年。産後ケア・産後ドゥーラ・母乳外来の専門の助産師です。
助産師・看護学校教員・市役所の母子保健コーディネーター等の経験を活かしてサポートします。
プロフィールを見る
目次
断乳とは何か?
断乳の定義と目的
「断乳」とは、赤ちゃんが母乳を飲むことを完全にやめるプロセスを指します。
授乳を減らすことで徐々に移行する場合もあれば、家庭の事情や母体の体調に合わせて短期間で進める場合もあります。
断乳の目的は、赤ちゃんが母乳以外の栄養をしっかり摂れるようにすること、そして母親の体を守ることにあります。
特に、食事や水分から必要な栄養がとれるようになると、断乳を進めても安心です。
ただし、断乳は単なる食生活の切り替えではなく、母子の心のつながりにも大きく関わります。
そのため、赤ちゃんと母親が安心して過ごせるように、断乳の時期をどう決めるか、どのような飲み物を用意するかなどを一緒に考えていくことが大切です。
母親自身も「もう進めてもいい」と思える心の準備ができているかどうかが断乳のポイントになります。
断乳と卒乳との違い
よく混同されやすい「断乳」と「卒乳」には明確な違いがあります。
卒乳と断乳の違い
- 卒乳:赤ちゃんが自らの成長とともに、徐々に母乳をやめること。自然な流れで進む。
- 断乳:母親の事情や体調、仕事復帰などを理由に、授乳を意図的にやめること。計画的に「やめる」場合が多い。
卒乳は「赤ちゃんが自然に母乳から卒業する流れ」であり、断乳は「母親が計画的に進める選択」といえます。
どちらも間違いではなく、家庭の事情や母子の状態に合わせて柔軟に選んでいくことが大切です。
「もう母乳を続けるのが難しい」と感じたときや、生活の変化に合わせたいときは断乳を選ぶケースもあります。
母乳をやめること自体が目的ではなく、赤ちゃんと母親が健やかに成長し、新しい生活のリズムを築いていくことこそが本当の目的です。
あわせて読みたい


卒乳とは?最適な時期とスムーズな進め方【現役の助産師が解説】
赤ちゃんとの大切な授乳の時間も、いつかは終わりを迎えます。 「そろそろ卒乳かな?」「まだ続けてもいいのかな?」——そんな悩みを抱えるママは少なくありません。 卒…
断乳はいつから?断乳の適切な時期
赤ちゃんの成長段階に応じたタイミング
断乳を考えるときに大切なのは、子どもの成長や発育の様子をしっかり観察することです。
一般的には6ヶ月を過ぎると離乳食を始められるようになり、母乳やミルクからの栄養の割合が少しずつ減っていきます。
ただし、断乳のタイミングは「〇ヶ月だから必ず」と決まっているわけではありません。
赤ちゃんの食事の進み具合や生活リズムに合わせて、適切な時期を判断することが大切です。
多くの家庭では1歳〜2歳を目安に断乳を検討しますが、それもあくまで一般的な目安にすぎません。
「いつ始めるのが正解か」は一人ひとり違います。無理に合わせるのではなく、赤ちゃんの成長と家庭の状況に沿ったペースで進めることが安心につながります。
母親の心身の準備
断乳は赤ちゃんだけでなく、母親にとっても大きな変化です。
まず、自分自身の気持ちを整理し、「断乳を始める準備ができているか」を確認しましょう。
体調も非常に重要です。産後の回復が不十分な場合や、疲れが強いときには、無理をせずに先送りにしても構いません。
断乳は自然な流れで進めるものですから、母親の健康や生活リズムが整っていることが前提です。
また、家族や友人の協力を得ることも大切です。特に夜間の対応や家事のサポートがあると、母親は心に余裕を持って断乳に臨めます。
妊娠をきっかけに断乳を考えるママもいますが、その場合も医師や助産師に相談しながら、無理のない始め方を選びましょう。
母乳トラブルは早期解決が重要です
断乳を始める前の準備
授乳回数の調整
断乳を始める前に、まずは授乳回数を少しずつ調整していきましょう。
いきなりやめるのではなく、段階的に進めることで赤ちゃんも安心できます。例えば、1日3回授乳していた場合には2回に減らし、その後1回に減らしていくとスムーズです。
大切なのは、赤ちゃんの反応をしっかり観察することです。
授乳の時間が短くても落ち着いて過ごせるようなら、回数をさらに減っても大丈夫なサインといえます。
ただし、まだ数ヶ月の小さな赤ちゃんにとっては母乳やミルクが栄養の中心となるため、早すぎる断乳は避ける必要があります。
母子ともに無理のないペースで進めることが、ストレスを少なくする可能を高めます。
段階を踏みながら「今日は以上頑張らない」と気持ちを緩めることも、安心して断乳を進めるコツです。
赤ちゃんの栄養状況の確認
断乳を進める前に欠かせないのが、赤ちゃんの栄養状況のチェックです。
 院長 岡田まどか
院長 岡田まどか特に早い時期(6ヶ月未満)の断乳には注意が必要です。必要量のミルクがしっかり飲めるか?体重増加が順調か?などを見てから判断することが大事です。
ミルク量や体重は、「日増計算」で測ることができます。
日増計算とは?
日増(にちぞう)計算とは、赤ちゃんの成長具合を体重で評価することです。
日増計算でわかることは、2つです。
- 体重が標準とおりに増えているかどうかの判断
- 哺乳量(母乳やミルクの量)が足りている・多すぎるの判断
サニー助産院の体重計は医療用で、g単位で体重測定ができます。
赤ちゃんの体重と日増計算の結果を比較すれば、感覚に頼らずに母乳量やミルク量の調整ができるようになります。


離乳食が十分に進んでいるか、主食・主菜・副菜を組み合わせてバランスのとれた食事になっているかを見直してみましょう。



サニー助産院では、離乳食アドバイザーの資格保有者や管理栄養士とのつながりがあります。
離乳食を始める際は、安心してご相談ください。
特に不足しやすいのは鉄分・カルシウム・ビタミン類です。これらが不足すると成長や体調に影響することがあるため、食材を工夫してしっかり補う必要があります。
たとえば、肉や魚、大豆製品、野菜や果物を組み合わせると安心です。
もし十分に摂れていないと感じたら、メニューの工夫や調理方法を見直して、必要な栄養をきちんと補う準備を整えましょう。
断乳のスタートは、赤ちゃんの健康な発育を支えるための重要なステップでもあります。
母乳トラブルは早期解決が重要です
断乳の具体的な方法
段階的な断乳の進め方
断乳をスムーズに行うための基本は、少しずつ授乳回数をやめる方向に調整していくことです。
いきなりやめるのではなく、1日の授乳を段階的に減らしていくと、赤ちゃんも安心して受け入れやすくなります。
たとえば、日中の授乳を先に減らし、夜間の授乳は最後まで残すというステップを踏む方法があります。このように「どの授乳から減らすか」を工夫すると、母子ともに負担が軽くなります。
大切なのは、赤ちゃんの様子をよく観察することです。機嫌が悪くなったり、不安そうにしているときは、無理に進めずにタイミングを見直しましょう。
その際に代替手段を用意することも有効です。母乳を飲まなくても安心できるように、おやつや麦茶、水などを取り入れると気持ちが落ち着きやすくなります。
断乳を進めるためのコツは、家庭や赤ちゃんの状況に合わせた方法を選ぶことです。
子どもの性格や生活リズムはそれぞれ異なるため、一つの方法に固執せず柔軟に対応しましょう。
急激な断乳を避ける理由
断乳を急に行うことは、母子ともに負担が大きくなるため避けた方が安心です。
母親の身体では、母乳の分泌が急に減ることで乳房が張りやすくなり、しこりや痛みが出る可能性があります。場合によっては乳腺炎などのトラブルを引き起こすこともあります。
一方、赤ちゃんにとっても急な変化は大きなストレスです。
授乳は栄養補給だけでなく、安心感を得る大切な時間です。それを急に絶たれると、夜泣きや不安定な行動につながることがあります。
このような理由から、断乳は段階的に行うことが推奨されています。
赤ちゃんの発達や家庭の状況を考慮しながら、無理のないペースで進めることが、母子にとって安心できる断乳の実現につながります。
断乳中の母親のケア
乳房のケア方法
断乳中は乳房が張りやすく、痛みや不快感を感じることがあります。
まず大切なのは、体に合ったブラジャーを選ぶことです。締め付けが強いものは血流を妨げ、乳腺の詰まりを悪化させることがあります。締め付けの少ない下着を選び、快適に過ごせるようにしましょう。
精神的なサポート
断乳は身体面だけでなく、母親の心にも負担を与えやすい時期です。
授乳がなくなることで「赤ちゃんとの特別な時間が終わる」と寂しさを感じることも珍しくありません。
そんなときは、一人で抱え込まずに家族や友人に気持ちを話すことが大切です。信頼できる人に相談するだけでも心が軽くなります。
また、読書や散歩、趣味など、自分に合ったストレス発散の方法を見つけておくと安心です。
場合によっては、助産師や医療機関に相談してみるのもおすすめです。
専門家によるアドバイスやカウンセリングを受けることで、心の不安がやわらぎ、安心して断乳を進められるでしょう。
あわせて読みたい

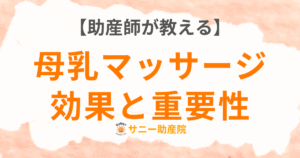
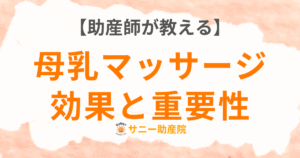
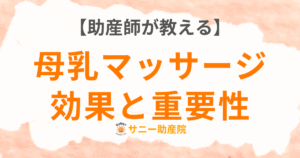
【助産師監修】母乳外来の母乳マッサージの効果と重要性を徹底解説(自己流はNG)
【無料LINE相談】母乳トラブルに悩むママ必見。母乳の出が悪い、授乳がつらいと感じる方へ。サニー助産院の院長・助産師歴20年の岡田まどかが、母乳マッサージの効果と正しい方法を分かりやすく解説。赤ちゃんが飲みやすくお母さんも快適に授乳できるよう丁寧にサポートします。
よくあるトラブルとその対処法
乳腺炎や乳房の張り
断乳の過程では、おっぱいに関するトラブルが起こりやすくなります。
特に注意したいのが乳腺炎です。
これは、乳腺に母乳が溜まったり細菌感染を起こしたりすることで炎症が生じる病気で、発熱、張った乳房の赤みやしこり、強い痛みが現れることがあります。
あわせて読みたい




【院長助産師が解説】母乳外来はなにするところ?相談内容と受診の流れ
「母乳外来ってなにするの?」そんな不安や疑問に、やさしくお答えします。 サニー助産院(栃木県小山市)は、助産師が個別の状態に合わせて授乳をサポート。外来はもち…
赤ちゃんの情緒的な反応
断乳は赤ちゃんにとっても大きな出来事です。これまで安心のよりどころだった授乳がなくなることで、不安を感じたり夜泣きが増えることがあります。
赤ちゃんが泣いたり不安そうにしているなら、まずはその反応をしっかり受け止めてあげましょう。
抱っこをして安心させたり、スキンシップを増やすことで「おっぱいがなくても安心できる」と感じるようになります。
また、赤ちゃんに分かりやすい言葉で「もう大丈夫だよ」と声をかけるのも効果的です。
赤ちゃんは親の声のトーンや表情からも安心を感じるため、日常的に愛情を伝える工夫をしましょう。
「母乳を欲しがる」場面も出てきますが、無理に遮断するのではなく、遊びや食事などで気を紛らわせながら少しずつ慣れさせていくことが、親子にとって自然な断乳の流れになります。
母乳トラブルは早期解決が重要です
助産師などの専門家に相談するメリット
専門的なアドバイスの重要性
断乳を考えるとき、専門家の知識や経験を活用することはとても大切です。
助産師や医師は、母乳育児に関する豊富な知識を持っており、赤ちゃんと母親それぞれの状況に合わせたアドバイスをしてくれます。
インターネットの記事や検索で得られる情報も参考になりますが、それだけでは十分とはいえません。
体調や生活環境は家庭ごとに異なるため、専門家による「個別のアドバイス」が必要になるのです。
また、最新の研究や臨床経験に基づくアドバイスは、より安心して断乳を進めるためのポイントになります。
サニー助産院のような母乳外来では、赤ちゃんの発達やママの体調に合わせた最適な方法をおすすめしており、心強いサポートになります。
母乳トラブルは早期解決が重要です
トラブル回避のためのサポート
断乳には乳腺炎や情緒不安定などのリスクがつきものです。
しかし、専門家に相談すれば、起こり得るトラブルを事前に知り、予防する方法を教えてもらえます。これは安心して断乳を進めるための大きな内容のひとつです。
たとえば、「授乳を減らすペースはどのくらいが推奨されるか」「乳房のケアはどのように行えばよいか」など、具体的な指導を受けられます。
さらに、夜間断乳や食事の工夫など、家庭ごとの事情に向けたアドバイスを受けることで、スムーズに移行が可能になります。
信頼できる専門家に紹介してもらった母乳外来や地域の支援センターを利用することも、断乳を安心して進めるために役立ちます。
正しい情報と適切なサポートを受けることで、母子ともに健やかな断乳を実現できるのです。
断乳後の生活
赤ちゃんの新しい生活リズム
断乳が完了すると、赤ちゃんの生活にはさまざまな変化が訪れます。
まず大切なのは、新しい食事の導入です。母乳やミルクに頼らず、固形食から栄養をとるようになるため、1日3回の食事を中心に、栄養バランスを意識して与えましょう。
離乳食から幼児食へと進む時期でもあるため、育児の中で「食べる習慣」を整えてあげることがポイントです。
次に、断乳によって睡眠パターンが変化することがあります。
夜間授乳がなくなることで、まとめて眠れるようになる子もいれば、逆に一時的に夜泣きが増える子もいます。赤ちゃんの反応を観察し、安心して眠れる環境を整えてあげると良いでしょう。
また、母乳以外で安心を得る必要があるため、遊びの時間を増やしてあげるのも効果的です。
日中の刺激やスキンシップは、赤ちゃんの発達を促進するとともにストレスの軽減にもつながります。
家庭や保育園での関わりを通じて、子どもの成長を支えていきましょう。
母親の心のケア
断乳は赤ちゃんだけでなく、ママにとっても大きな節目です。
授乳が終わることは喜びや解放感と同時に、寂しさや不安を伴うこともあります。
まずは、自分の気持ちを整理し、感じている感情に意味を与えることが大切です。
一人で抱え込まず、家族や友人に気持ちを打ち明けることも有効です。
支えてもらうことで、気持ちが軽くなり、心の安定につながります。断乳は母と子がともに成長するプロセスであり、母子にとって自然な流れです。
さらに、自分自身のケアとしてリラックスできる時間を持つことを意識しましょう。
趣味に取り組む、短時間でも休息をとるなど、心を整える時間を確保してください。
断乳後に気分の落ち込みや強い不安が続く場合には、専門家に相談して必要に応じた治療を受けることも安心につながります。
断乳は子育ての中で避けて通れないプロセスですが、それを乗り越えることが母と子の絆を深める大切なステップとなります。
母乳トラブルは早期解決が重要です
家族全体で支える断乳:父親・家族の役割とサポート方法
断乳は母親と赤ちゃんだけの出来事に見えますが、実際には家族全体で取り組めると理想的です。
パートナーや祖父母、兄弟姉妹などがサポート役を担うことで、母子の負担を大きく減らすことができます。
父親の役割
断乳中、赤ちゃんは「おっぱいが欲しい」と泣くことがあります。
そんなときにパパが抱っこして寝かしつけをすることで、赤ちゃんは母乳以外の安心感を得られます。
また、夜間の対応を父親が分担することで、母親の休息時間を確保できるのも大きな助けです。
さらに、家事を積極的に引き受けたり、育児の一部を担当したりすることで、母親の心身の負担が軽減されます。
父親が「一緒に乗り越えよう」という姿勢を見せることが、母親にとって大きな支えになります。
祖父母のサポート
祖父母は、断乳期の育児を支える大切な存在です。
赤ちゃんと遊ぶ時間を増やしたり、外出時に付き添ったりすることで、母親が安心して休める時間を確保できます。
祖父母の経験から得られるアドバイスも心強いですが、古い習慣が現在の育児法と違う場合もあるため、母親の気持ちを尊重しながら協力してもらうことが大切です。
兄弟姉妹との関わり
断乳は下の子にとって大きな節目ですが、同時に上の子にとっても変化の時期です。
「どうして弟(妹)ばかり?」と寂しさを感じやすいため、上の子と一緒に過ごす時間を意識的に増やしましょう。
上の子に簡単なお手伝いをお願いすることで、「自分も赤ちゃんをサポートしている」と感じられ、きょうだいの絆を深めるきっかけになります。
家族での協力体制
断乳は単なる「授乳をやめる」ことではなく、家族全体の生活リズムが変わる大切な転機です。
食事や睡眠のパターンが変わる中で、協力して対応することが母子の安心につながります。
NPOサニーベイビーズとは?


産後ママと赤ちゃん(1歳3ヶ月未満)を対象にした産後ケアサークルです。(登録無料)
産後ママの交流を目的に、産後ケアイベントを月1回開催しております。
断乳後の子どもの情緒と心理的変化:安心して成長を促すケア方法
断乳は赤ちゃんにとって、これまでの安心のよりどころであった授乳がなくなる大きな転機です。
そのため、身体的な変化だけでなく、情緒や心理面でも影響が出ることがあります。
子どもの心理的変化
断乳後の赤ちゃんは、不安を感じて泣いたり、夜泣きが増えたりすることがあります。
母乳を通じて得ていた安心感がなくなるため、一時的に気持ちが不安定になるのは自然なことです。
また、甘えが強く出たり、ママに「抱っこ」を求める頻度が増えることもあります。
この時期は「授乳がないと安心できない」という気持ちを理解し、代わりの安心手段を与えてあげることが大切です。
安心を与えるケア方法
- 抱っこやスキンシップを増やす:身体のぬくもりは、授乳に代わる安心感を与えます。
- 言葉かけを意識する:「大丈夫だよ」「そばにいるよ」と声をかけることで、子どもは安心を感じやすくなります。
- 遊びや生活リズムで支える:遊びや日常の習慣を安定させることが、子どもの心を落ち着ける助けになります。
成長を促すために
断乳は、子どもが母乳に頼らず自立へ一歩進む大切な機会でもあります。
不安を和らげながら生活を整えることで、子どもは少しずつ「自分で安心できる力」を身につけていきます。
ママや家族が温かく寄り添うことで、断乳後の情緒的な揺れも次第に落ち着き、安心して新しい生活へと移行できるでしょう。
母乳トラブルは早期解決が重要です
母体の健康変化と断乳後のセルフケア
断乳は赤ちゃんだけでなく、母体にも大きな影響を与えます。
授乳がなくなることでホルモンの分泌バランスが変化し、体調や気分に揺れを感じることがあるため、母親自身のケアも欠かせません。
ホルモンバランスの変化
授乳によって分泌されていたホルモン(プロラクチンやオキシトシン)は、断乳後に徐々に減少していきます。
この変化により、気分が落ち込みやすくなったり、体の疲れを強く感じたりすることがあります。
これは一時的なものですが、「自分の体に変化が起きている」と理解しておくことが安心につながります。
体調管理のためのセルフケア
- 睡眠をしっかり取る:夜間授乳がなくなる分、まとまった睡眠を取るように心がける。
- 栄養バランスの良い食事:鉄分・カルシウム・ビタミンを含む食材を取り入れて、体の回復をサポート。
- 軽い運動:ストレッチや散歩などで血流を良くし、気分を整える。
これらは特別なことではありませんが、日常的に意識して行うことで体調を安定させることができます。
心のケア
断乳を迎えると、「子育てが一区切りついた」という達成感と同時に、「あの授乳時間が終わってしまった」という寂しさを覚えることもあります。
こうした感情は自然なものであり、否定する必要はありません。
不安やストレスを感じたときは、信頼できる人に気持ちを話したり、リラックスできる時間を持つことが大切です。
気分の落ち込みが長く続く場合には、医療機関や助産師に相談し、必要に応じたサポートや治療を受けましょう。
断乳は母子にとって新しいスタートです。
母親自身の健康を大切にしながら過ごすことで、親子ともに安心して次の成長ステージへ進むことができます。
母乳トラブルは早期解決が重要です
